故人にかかわりのあった友人や知人、お取引先様に声を掛け、故人の足跡をたどる場として、
また、お互いが感謝する場として、催す『お別れの会』。
ネクストページは、ご遺族のご希望やご意向に沿いつつ、故人の人生に敬意を払い、ご遺族や参会者の心に残る送別の機会を創りあげるべく、
「お別れの会」「偲ぶ会」「社葬」を、きめ細やかにプロデュース(企画・準備の代行)いたします。

エンディングプランナー・小池です。家族葬の後行なわれる、お別れの会偲ぶ会について連載しています。開催会場で最も多いのはホテルです。交通利便性が高く、使い勝手が良いからです。しかし、予算面が理由で利用料が安価な公共施設を利用する場合が有ります。安価ではありますが、準備・後片付けは全て主催者側で行なうことになります。その内容をご紹介します。① 祭壇設営場所に養生シートを床に張る ②会場を設営する(祭壇・献花台・手荷物置き台・花置き台・受付・記帳台・テーブル・イス) ③必需品を置く(献花を置く黒盆・筆記用具・マット・芳名カード・出席者リスト) ④映像を再生する場合、スクリーン・プロジェクターを設置する ⑤遺品を展示する ⑥ディレクター(進行担当・現場監督)は音響・照明担当者に指示をする ⑦映像再生担当者はリハーサルを行なう ⑧飲食を提供する場合、必需品を用意する (グラス・皿・箸・ナイフ・スプーン・フォーク・ナプキン・生ごみ用袋・紙製品用ごみ袋) ⑨飲食を提供する場合、養生シートを床に張る ⑩食材を購入する ⑪料理を器に盛る ⑫飲料を購入する ⑬飲料を並べる ⑭使用後のグラス・皿を片付ける ⑮ゴミをまとめる ⑯ゴミを持ち帰る ⑰テーブル・イスを片付け、原状復帰する ⑱掃除する 以上です。PROFILE エンディングプランナー 小池 中 Ataru Koike お気軽にお電話または、お問い合わせフォームよりご連絡くださいませ。 お別れの会に関するよくあるご質問はこちらから

エンディングプランナー・小池です。家族葬の後行なわれる、お別れの会偲ぶ会について連載しています。進行方法(プログラム)は、大きく分けると2種類有ります。その一つは「流れ献花方式」です。受付→献花→歓談→退出というステップです。もう一つは、「セレモニー方式」です。こちらが全体の9割に及んでいます。受付→献花→着席→開式→①黙とう②主催者挨拶→③家族代表挨拶→④追悼の言葉→閉式→⑤献杯(の発声)→歓談(食事)開始と進みます。最近は、動画(スライドショー)再生が8~9割に及んでいますので、それを式典の冒頭か、式典のプログラムの一つにする、という選択肢が有ります。勿論、歓談中も同じ物を再生し続ける方法もあります。 なお、式典(セレモニー)は、30分以内が一般的ではあります。PROFILE エンディングプランナー 小池 中 Ataru Koike お気軽にお電話または、お問い合わせフォームよりご連絡くださいませ。 お別れの会に関するよくあるご質問はこちらから

エンディングプランナー・小池です。家族葬の後行なわれる、お別れの会偲ぶ会について連載しています。 お別れの会偲ぶ会の会場として、最も利用されるのはホテル宴会場です。ホテルの場合、季節・月・曜日・時間帯によって利用料が異なります。春の3~6月、秋の9~11月は婚礼が優先するため、開催希望日の2ヶ月前で初めて、空きが出ます。その婚礼シーズンの土曜日曜祝日は、宴会場が空いていても婚礼客に気を遣って取りにくいのが現実です。また、飲食の有無によっても宴会場利用料は違います。飲食が伴う場合、室料は大幅に下がります。室料に限って言えば、平日の昼間、また、昼食時間帯を除いた午後が、最も安価になっています。なお、夜の時間帯も考えられますが、参会者が高齢な場合、避けられています。PROFILE エンディングプランナー 小池 中 Ataru Koike お気軽にお電話または、お問い合わせフォームよりご連絡くださいませ。 お別れの会に関するよくあるご質問はこちらから

エンディングプランナー・小池です。家族葬の後行なわれる、お別れの会偲ぶ会について連載しています。 最近、お別れの会偲ぶ会では、写真や動画を演出に使うことが多くなりました。写真の場合、①遺影、②額入り写真、③写真パネル、④しおりなどに使いますが、会当日、記録に残すという目的から、スナップ写真や集合写真を撮影しています。また、最も多い演出方法はスライドショーです。50~100の写真を選び、7分~15分のスライドショーに仕上げます。再生する場面は、Ⓐ受付開始から開会まで、Ⓑセレモニーの一プログラムとして、Ⓒ歓談(食事)時間帯でです。一方、動画も貴重な演出方法です。写真と動画をまとめるとより効果的です。再生場面は上記Ⓐ~Ⓒと同じです。ところで、開会から閉会まで動画撮影し、途中、参会者にインタビューして故人の思い出やエピソードを語ってもらう方法も有ります。PROFILE エンディングプランナー 小池 中 Ataru Koike お気軽にお電話または、お問い合わせフォームよりご連絡くださいませ。 お別れの会に関するよくあるご質問はこちらから
家族葬(密葬)の後、1ヶ月前後経ってから行うお別れの会・偲ぶ会(しのぶ会)・社葬について
詳細を見る

立食・着席など参会者の人数や、セレモニーの内容により最適なスタイルをご紹介いたします。
詳細を見る

ネクストページはお別れの会、偲ぶ会(しのぶ会)、社葬のプロデュース・プランニングを専門とする会社です。弊社がご提案する『お別れの会』では、一般的な葬儀にはない演出を施し、故人の人生を振り返り、故人の意外な一面を知って頂くことで、故人の人生を讃える一方、ご遺族や参会者の心に残る、送別の機会をご提供します。
また、お取引先様、従業員の皆様が集うことで、故人とのご縁を、お別れの会後へも引き継いでいく機会とするお手伝いも致します。
ネクストページは、ご遺族のご希望やご意向に添いつつ「故人の人生に敬意を払う感動的なお別れの会」を創りあげるべく、トータルプロデュース及びサポートを致します。
迅速な会場の仮予約と、その後原則24時間以内にご指定の場所へ伺い詳細のヒアリング・ご提案をさせていただきます。

複数会場から入手した見積書を基に、主催者様と最適な会場・プランを検討、お選びさせていただきます。(無料)

初めにご要望をお聞きする担当者(フェアウェルプランナー)が、当日会場での総指揮まで、一貫して担当致します。

ご案内状の作成・筆耕・投函や出欠の取りまとめ、参会者からのお問い合わせへの回答なども主催者に代わって行います。

祭壇は低価格で高品質とご評価を頂いております。思い出写真のパネルや映像お任せ下さい。(遺品展示例)
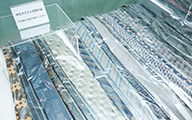

お別れの会・偲ぶ会・社葬の参会者50名の場合のプラン例をご紹介しております。会場、演出やご予算などに応じて柔軟なプランニングを心がけておりますので、遠慮なくご希望をお聞かせ下さい。

お別れの会・偲ぶ会・社葬当日までの事前準備と、当日の進行スケジュール例をご紹介いたします。事前準備から進行まで、ネクストページではトータルに主催者様をサポートさせていただきます。

地下鉄「大手町駅」C13出口より地下通路直通
JR「東京駅」丸の内北口より徒歩8分

・JR「東京駅」丸の内南口直結
・JR「東京駅」新幹線中央乗換口より徒歩1分
・東京メトロ丸の内線「東京駅」より徒歩3分

◆JR山手線・目白駅からバスで10分 目白駅改札前の横断歩道を渡り、
左手のバス停5番乗場「目白駅前」より都バス新宿西口行き、
または右手側の8番乗場「川村学園前」よりホテル椿山荘東京行き、新宿西口行きにて
「ホテル椿山荘東京前」下車。所要時間約10分料金大人210円(IC:206円)
◆東京メトロ有楽町線・江戸川橋駅から徒歩で10分
東京メトロ有楽町線「江戸川橋」駅1a出口から地上に出て、神田川の橋(江戸川橋)を渡り、約30m先ひとつめの信号(八百屋の角)を左折。道なり(坂道)に約500m
◆無料シャトルバス※土日祝日のみ運行
池袋駅西口7番停留所⇔ホテル椿山荘東京(ノンストップ)所要時間約20分

各線地下鉄「溜池山王駅」13番出口より、徒歩1分
南北線「六本木一丁目駅」 3番出口より徒歩2分(六本木一丁目駅より約5分)
弊社の実績豊富なフェアウェルプランナーが親切丁寧にお応えいたします。
費用の概算、おすすめの会場、開催の時期、プログラム、お別れの会・偲ぶ会・社葬の違い…など